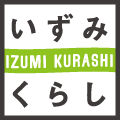歩いて行ける里山には宝物がいっぱい! 楽しく自然をまもる天王森泉公園の人々
皆さんは和泉町にある「天王森泉公園」をご存じでしょうか。
そこには美しい歴史的建造物が静かに構え、いい香りのする草花や森があり、澄み切った湧水がこんこんと水をたたえています。鳥たちのおしゃべりを聞きながら進むと、そこにはなんとワサビ田があり「本当に横浜?」と驚きを隠せません。
聞けば、いずみくらしのライターにも複数のファンがいました。公園の管理は、地域住民が主体の運営委員会が行っているとあり興味津々です。今回は天王森泉公園の魅力と、それを支えるボランティアについて取材を行うべく、年明け早々に公園へ向かいました!
相模野台地の崖線から湧く豊富な湧水を活かして、和泉川流域は20に上る製糸場が営まれた歴史があります。約38,000㎡(サッカーコート約5個分)の公園敷地には多くの草木が森をつくり、多種多様な生き物が生まれます。餌を求めて、昆虫や野鳥、小動物が集まる自然豊かな環境が、私たちの住まいのすぐ近くにあるのです。
正面入り口から敷地に踏み入ると、足元で玉砂利が鳴り、心地よく感じます。
「音で気づいたのか、係の方が出てきて温かく迎えてくださった」とライター仲間も感銘を受けた、日本人らしい心遣い、おもてなしがありました。
天王森泉館:よりどころ、憩いの場、体験施設としての機能も
「泉館」は、明治時代に清水製糸場の本館として建設。泉区一帯では江戸時代から養蚕が行われ、明治には横浜港貿易と結びついて製糸産業が盛んになり、大正時代にピークを迎えました。その後、製糸産業の衰退を経て、昭和初期に現在の敷地に移築され、個人宅として利用されましたが、平成9年の公園整備の際に利用しやすいように一部改修し、公園の拠点施設として活用しています。
湧水の森:ここは横浜?非日常を感じられる清らかな空間
本館の左脇を行くと大池とせせらぎがあり、6月初旬には30~40匹のゲンジボタルが乱舞します。その奥からはこんこんと湧水が流れ、なんとワサビ田が! 公園以前より土地を所有していた方が造ったワサビ田を存続すべく、ワサビ田チームがワサビを食べてしまう虫を取り除き、現在は景観として維持しています。
隣には孟宗竹の林があり、草刈りや伐採などの手入れをして、春には美味しい竹の子が出てきます。近くでは落ち葉の堆肥づくり、日陰では原木しいたけの栽培も行い、この空間を活用しています。
野の花苑は四季を彩る野草の庭です。1月は凛とした空気の中に蝋梅(ろうばい)の香りがふわりと伝わり、センリョウやマンリョウの赤い実が光ります。2月初旬には春を告げる福寿草が顔を出し、中旬にはしだれ梅のやさしいピンクが寒さで固くなった心をほどくようでした。
見晴らしの丘:滑って転んで捕まえて!楽しい広場
野の花苑の脇の道を上がっていくと、植栽された樹木と草原の広場があります。近くの保育園から子どもたちがお散歩で遊びにくると、景色のよい高台から段々の斜面を滑り台にして大喜びだそうです。草原にはバッタなど多くの虫がいて、成虫のまま越冬する虫も見られます。
くわくわ森:カブトムシやクワガタムシはいるかな?
この森は元々、近辺の農家の薪や炭、落ち葉の堆肥をつくるためにクヌギやコナラを植えた薪炭林(しんたんりん)でした。ナラ枯れで伐採され、それがあることで育っていた林床の草花の保全が難しくなり、苗木を育てることに。ドングリから育った苗に、目印の竹の棒が立ててあるので、探してみてください。
田んぼ:田植え、稲刈り、もちつきは公園の大きな行事
くわくわ森の前にある田んぼでは、園内から湧く豊富な湧水で米づくりも行われています。「米」という字は「八十八」と書きますが、それだけの手間をかけ、土づくりから育苗、田植え、除草などの管理をして10月に収穫します。地域の子どもたちの体験の場でもあります。
生き物調査観察会:鳥も、虫も、花も! わいわい覗くレンズの先
生き物調査観察会は、毎月第1火曜日の9時から15時の間に活動しています。小さなお子さんでも参加可能です。時間は自由に出入りができ、お昼ご飯を持参して1日参加される方も。私も双眼鏡や虫眼鏡をお借りして鳥や虫、花を観察しました。とても詳しく教えていただけるので楽しく、夢中になりました。
地域の特色を活かし、地域の人がつくる公園
公園開設にあたり、地域住民と横浜市が協力して約3年の計画づくりをしたそうです。平成9年の開園までの流れについて、事務局長と運営委員会の皆さんにお話を伺いました。
この一帯は清水製糸場を営んだ清水家から、清水家のご令嬢が通う学校の先生に持ち主が移り、その方が湧水を活かしてワサビ田や竹林、池をつくり、薪炭林はそのままにされていたそうです。「館が横浜市に譲渡される際に公園にすることとなり、愛護会ができました。運営と管理が分かれていたのがひとつになったのが運営委員会のはじまりです」と副会長の山本登久(とく)さん。
横浜市と地域住民の話し合いには子どもたちも参加。登久さんは「くわくわ森の名前は、公園になる前から子どもたちにそう呼ばれていたため、そのまま残したそうです。館の横に流れる水路で水遊びがしたいというのも、子どもたちからの要望でした」と言います。
こうして地域住民の声をひろい、アドバイザーとして南部公園緑地事務所から指導を受け、エリアごとの特色を活かしながら「ここは子どもが喜ぶところに」「ここにホタルの住処を」「ここはお客様に楽しんでいただこう」と目標を決めて整備・管理してきました。
「環境の変化を感じ取りながら、いま必要な仕事を自分たちで見つけていくことが大切。生物多様性を実現するには、ここは機械で、ここは手刈りで、と細やかに対応する必要があります」と登久さん。
民間の会社では都合上、どうしても画一的な管理になりがちであることから、天王森泉公園では地域住民が主体となる運営委員会、ボランティアによる管理という方法を選んでいます。
ホタル育成グループ:ゲンジボタルに住んでもらう環境づくりを
この辺りは公園になる前から湧水がありホタルがいました。その昔、愛好家たちが「ホタル研究所」と称してホタルを購入、繁殖して放していたそうです。この湧水のある研究所跡地を復活させ、ホタルが自然繁殖する環境づくりをしているのがホタル育成グループです。
「ホタルの住む場所が減っています。飛べる範囲に住む場所がいくつもあれば、ホタルが行き来できます」「餌のカワニナ(貝)が増える環境づくりが必要です」とリーダーの水越利春さん。ホタルの行き来ができないと近親交配が進み、奇形や病気のリスクが高まり、繁殖力が落ち、種が絶えてしまいます。
これまでコンサルタントの助言を受けながら、泥池にカワニナの餌であるコケや藻が繁茂するよう、木を切って日当たりをよくして、覆っていた草を刈り、三段の池とホタルの好むせせらぎの道をつくりました。同じ水系の田んぼにいたカワニナを泥池に入れたところ定着。定期的にカワニナをホタルが住みつくせせらぎに移しています。
「メスは長年、繁殖に適した場所から動きません。オスは繁殖相手を探して飛び回ります。ホタルの住む場所が複数あることでオスが行き来をしてDNAが混ざり合います」と教えてくれたのは、ボランティアの山本厳(がん)さん。
田んぼの水路に出るホタルが飛んできて、ここに住む場所があると気づいてくれたら!と私も願わずにはいられません。
ホタルの減少について「LEDの光が強くホタルは繁殖相手が見えない」と登久さん。街の明かりはもちろん、車のライトや街灯も原因になります。人間にとっては見やすく省エネなLEDですが、ホタルの繁殖に影響を及ぼすものだと知り、考えさせられます。
公園ボランティアで楽しみながら、話して動いて健康に!
長年、活動をされている登久さんは「ボランティアは楽しみながらできるのが一番!」と笑顔で話します。「ボランティアには“奉仕”のイメージもあるが、そればかりだとつまらない。自分も楽しみながらやっているから続けていける」その言葉に強く惹かれ、私も興味が湧いてきました。
<ボランティア参加の流れ>
- 事務局に連絡
- 「どこをやりたい?」と要望や得意・苦手を確認、好きなところから始める
- いろいろ試して、好きなエリアや行事、作業に定着する
登録すると事務局からメールや手紙で「ボランティア通信」が送られ、作業や行事を確認できます。ベテランボランティアによるサポートや研修・勉強会もあり、初心者でも安心です。
この地域の宝物「天王森泉公園」を一緒に守りたい
運営委員会会長の角本等さんからは、活動を通して「社会貢献、人に喜ばれる」ことが「自分の人生を豊かにする、ゆるやかなボランティア」だと教えていただきました。
湧水の森のベンチに座り、たぬきやフクロウを保護した話から、アオダイショウがタイワンリスを丸呑みにした話まで、笑ったり驚いたりしながらお話を伺い、私もすっかり穏やかな気持ちになりました。
桜が咲き、4月中旬の竹の子まつりでは竹の子汁が振る舞われます。「歴史と自然を受け継ぎ、みんなに愛される天王森」を、ぜひ訪れてみてください。心温まるおもてなしと美しい里山の景色に出会えますよ!
##ライタークレジット:
文=横山真由美 写真=石井豊、蒲喜美子、横山真由美
取材協力=石井豊、蒲喜美子、松本裕美枝、一柳亮太
##Information:
天王森泉公園
電話/FAX:045-804-5133(ボランティアの参加も事務局へ)
住所:横浜市泉区和泉町300
Email:izumi@tennoumori.net
Instagram:https://www.instagram.com/tennoumori_official
開園時間:9:00~17:00
休館日:第2・第4火曜日(祝日は翌日)年末年始12月29日~1月3日
アクセス:駐車場がありませんので、車での来園はご遠慮ください
市営地下鉄ブルーライン「下飯田駅」より徒歩25分
相鉄いずみ野線「ゆめが丘駅」より徒歩30分
神奈中バス「四ツ谷」バス停より徒歩15分
神奈中バス「ドリームハイツ」バス停より徒歩15分
※このコーナーの記事は、泉区が大好きな「泉区ローカルライター」が、区民の目線で取材し、執筆しています。
一覧をみるフラワーアークが心を込めて育てる 彩の花苗とフレッシュないちじく